Copyright © Jackie,2002-2006
ラリーな用語集
このページでは、ラリー特有のものも含め、いろいろと出てくる用語を紹介していきます。
記載の内容については、できるだけ正確性を心がけしましたが、万一誤りなどがあれば、ご連絡ください。
- 1000湖ラリー
- →フィンランド・ラリー
- APRC
- Asian Pacific Rally Championship の略で、アジア・パシフィック・ラリー選手権のこと。日本では「アジパシ」とも言われています。
- FIV
- First Intervention Vehicle の略で、ラリードクターが待機する救急車のような存在のオフィシャルカー。各SSのスタート地点に配され、万一コース上でアクシデント(事故)が発生した場合には急行し、救急処置を行います。
このFIVとは別に専用救急車も準備されています。
- M-Sport
- ご存知、フォード・ラリーチームを運営しているイギリスに本拠地を置く会社です。代表はマルコム・ウィルソン (Malcolm Wilson) 。開業当時の名称は「マルコム・ウィルソン・モータースポーツ」。名前を縮めて、現在の名称になりました。
なお、BMWのスポーツキット装着コンプリートモデルも「Mスポーツ」という名称がつけられていますが、全く別のものです。
- OMCP
- Odometer Check Point (オドメーター・チェック・ポイント)の略で、実走距離の誤差を修正するために用意されている区画のことです。
ラリー車には、タイヤや計器の個体差があるため、実際にコースを走行し、これらの誤差の補正係数を計算できるようにしているものです。
- PSA
- 正式名称は「PSAプジョー・シトロエン」で、プジョーとシトロエンのグループ親会社のことです。つまり、プジョーとシトロエンは兄弟の関係にある、と言うことです。
- SS
- Spesial Stage の略で、一般交通を遮断した競技専用コースでタイムアタックを行う区画です。WRCでは、このSSの合計タイムで順位を決めています。
- Sタイヤ
- スリック・タイヤのことを指します。
- TC
- →タイムコントロール
- アイテナリー
- 原語では、"Itinerary"。「行程表」の意味で、プログラムのようなものと考えていただければよいでしょう。
- アジパシ
- →APRC
- グラベル
- いわゆる「未舗装路」のことです。日本では「ダート」と呼ぶこともあります。
対して、舗装路(アスファルト路面)は「ターマック」といいます。
- グラベルクルー
- グラベルノートクルーと呼ばれることもあります。SSの最終下見を行うドライバーのことです。
マニュファクチュアラー・チームは、SSが閉鎖される直前、グラベルカーと呼ばれる下見車を走らせることができます。このドライバーがグラベルクルーで、彼らは本番用のペースノート(→)を持ち込み、レッキ(→)中には無かった変化や最新の路面状況などを調べて、サービスパークにいるスタッフに連絡します。これを受けて、ペースノートを変更したり(多くは危険箇所の追加らしい)タイヤ選択を行います。
そのため、グラベルクルーには引退したラリードライバー(有名な人も多いらしい)が抜擢されることがあるそうです。
- コドラ
- →コドライバー
- コドライバー
- 正しくは「コ・ドライバー」で、直訳すると「副運転手」。その役割から、ナビゲーターと呼ばれることもあります。
ラリー中は助手席に座り、SS(→)でペースノート(→)を読み上げたり、ロードセクションではTC(→)までの時間や距離を調整したり、とにかく仕事量が多いんです。
もちろん、非常事態には、その名のとおりラリーカーを運転することもできます。
- コンパウンド
- ラリー競技のなかで使用される場合、それはタイヤの接地面に使用されるゴムの種類のことです。柔らかいと、グリップ(タイヤの接地力)が得られるものの磨耗には弱く、硬いと、グリップは落ちるものの耐久性が増すわけです。路面の状況に応じてタイヤの種類を替えることが、良いタイムを出すために必要になってくるわけです。
ラリーの解説を聞いていると「ハード・コンパウンド」とか「ソフト・コンパウンド」といった単語をよく耳にすると思います。
- シェイクダウンテスト
- 競技の前日(ラリーウィークの木曜日)に、主催者が用意した区間(もちろん本番区間は含まれない)を試走し、マシンの最終チェックを行うものです。
- スペシャルステージ
- →SS
- スーパーSS
- →スーパースペシャルステージ
- スーパースペシャルステージ
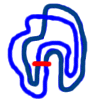 SS(→)とは異なり、閉鎖された非公道を使用する競技で、閉鎖された特設ステージで2台のマシンがタイムアタックをするものです。右の模式図のような立体交差を利用した特設コースを2台が同時に走ります。赤で示したスタート地点から2台が青と紺の別々のルートを出発します。1周すると、相手のスタート地点になり、さらにもう1周を走って、結果として自分のスタート地点に戻ってくるタイプのものですので、直接競り合うことはありません。
SS(→)とは異なり、閉鎖された非公道を使用する競技で、閉鎖された特設ステージで2台のマシンがタイムアタックをするものです。右の模式図のような立体交差を利用した特設コースを2台が同時に走ります。赤で示したスタート地点から2台が青と紺の別々のルートを出発します。1周すると、相手のスタート地点になり、さらにもう1周を走って、結果として自分のスタート地点に戻ってくるタイプのものですので、直接競り合うことはありません。
- タイムカード
- いわゆる「タイムカード」を想像していただければいいでしょう。
定められた時間どおりにTC(→タイムコントロール)を通過しているか、などを記載するカードで、その早着や遅着はSSのタイムに影響してきます。
- ターマック
- アスファルト路面、いわゆる「舗装路」のことです。
対して、未舗装路は「グラベル」といいます。
- パルクフェルメ(Parc Ferme)
- 一切の整備・補修などが禁止される区間や場所のこと。
スタート前の車両保管など、競技車両を使用しない時間は、競技車両は一箇所に集めて管理され、勝手に整備したりできないようになっています。
語源は「閉ざされた公園」という意味のフランス語。
- パンクチャー(puncture)
- いわゆるパンクのこと。英語では、一般的にパンクのことを "flat tire" と表現しますが、ラリーではドライバーのインタビューなどを聞いていると、パンクチャーといっています。
ムースタイヤ(→)のおかげで、パンクしても走ることができるため、パンクしている状態でもタイヤはフラット(平ら)にはなっていません。そのため、パンクの意味を持ち、尖った物などで小穴が空いた状態を指す "puncture" を多用するものと思います。
- フィンランドGP(フィンランド・グランプリ)
- フィンランド・ラリー(→)のことで、超高速のグラベルラリーのため、そのスピード感から、F−1のグランプリに匹敵することを表した呼称です。
- フィンランド・ラリー
- 50年以上の長い歴史の中で、ノンスカンジナビアン(スカンジナビア出身者以外)の優勝者はアリ・バタネン、カルロス・サインツ、そしてわれらが「マルコ・マーティン」の3人だけ。フィンランド人にとっては、ワールドチャンピオンを獲るのと同じほどの重要性を持つといわれる、伝説の超高速グラベルラリーです。
- フライング・フィン
- "Flying Finn"、"Finn" は Finnish (フィンランド人)のことで、「飛ぶように早く走るフィンランド人のラリー・ドライバー」を意味する敬称、いや「称号」ですね!
ミスターWRC、帝王「トミ・マキネン」や「マーカス・グロンホルム」などが有名ですね。
F−1でも、キミ・ライコネンがやはりフィンランド出身です。
- ポディウム
- 表彰台のこと。台そのものだけではなく、象徴としても用います。
例)ポディウムをかけた、熾烈な3位争い
- ホモロゲーション
- 一般に「公認」と訳されます。ラリーカーはFIAの定めた規則に則って作成される必要がありますが、この規則によって認められたものを指します。これは車両本体からパーツまですべてに及びます。日本では一般に「ホモロゲ」と略されますね。
純正パーツだからといって、必ずしもホモロゲーションが取得されているわけではないので、国内ラリーのラリーカーを作成するのは素人だけでは難しいんです。
- マニュファクチャラー(マニュファクチャラーズ)
- マニュファクチャラーは、英語で書くと" manufacturer "。つまりメーカーのことです(辞書引いてみてください(^^;)。WRCでは、ドライバーだけではなく、メーカー公認(主導)のチームにもポイントが与えられ、文字通りメーカー同士の戦いという側面もあります。このポイントが「マニュファクチャラーズ・ポイント」です。
- マニュファクチャラーズ・ポイント
- →マニュファクチャラー
- ミニティーシート
- レギュレーションに違反していないものの、ホモロゲーション(→)が取得されていないものがあれば、当然、「違反してないよ」と示す書類が必要ですよね。これがミニティーシートです。つまり、業者が作成する仕様書のようなものと思っていただければよいと思います。
- ムース
- →ムースタイヤ
- ムースタイヤ
- タイヤがパンクした際、内部のムースシステムが作動、空気が満たされていた部分に「ムース状」にスポンジが膨張してタイヤに強度を与えるシステムです。ラリーステージによって、ターマック(→)用、グラベル(→)用、スノー用が存在します。15cmほどの穴までならば対応できるっていうんですから驚きですよね!
ミシュランは「ATS」、ピレリは「EMI」という名称を使用しています。
- リバース・オーダー
- SS(→)の出走順が、暫定順位(前SSまでの順位)の下位からとなること。
- レグ
- 実際には厳密な規定があると思いますが、競技1日をまとめて「レグ」と考えると分かりやすいと思います。
初日を「Leg 1」(レグ・ワン)、以降レグ・ツー、レグ・スリーと続きます。
- レッキ
- 競技区間の下見で、通常は2回まで許可されています。通常は、この時点でより詳しいペースノートを作成します。
公道を使用する性質上、一般車両に混じって走行するので、現地の交通法規を尊守する必要があるのが特徴。天候が悪くてもやり直しはありません。
英語の "reconnaissance" (リコナイサンス)が訛ったのが語源。
モータースポーツのDVDは、ここから探してね!
再読み込み(リロード)すると商品が変わります
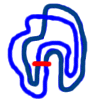 SS(→)とは異なり、閉鎖された非公道を使用する競技で、閉鎖された特設ステージで2台のマシンがタイムアタックをするものです。右の模式図のような立体交差を利用した特設コースを2台が同時に走ります。赤で示したスタート地点から2台が青と紺の別々のルートを出発します。1周すると、相手のスタート地点になり、さらにもう1周を走って、結果として自分のスタート地点に戻ってくるタイプのものですので、直接競り合うことはありません。
SS(→)とは異なり、閉鎖された非公道を使用する競技で、閉鎖された特設ステージで2台のマシンがタイムアタックをするものです。右の模式図のような立体交差を利用した特設コースを2台が同時に走ります。赤で示したスタート地点から2台が青と紺の別々のルートを出発します。1周すると、相手のスタート地点になり、さらにもう1周を走って、結果として自分のスタート地点に戻ってくるタイプのものですので、直接競り合うことはありません。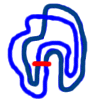 SS(→)とは異なり、閉鎖された非公道を使用する競技で、閉鎖された特設ステージで2台のマシンがタイムアタックをするものです。右の模式図のような立体交差を利用した特設コースを2台が同時に走ります。赤で示したスタート地点から2台が青と紺の別々のルートを出発します。1周すると、相手のスタート地点になり、さらにもう1周を走って、結果として自分のスタート地点に戻ってくるタイプのものですので、直接競り合うことはありません。
SS(→)とは異なり、閉鎖された非公道を使用する競技で、閉鎖された特設ステージで2台のマシンがタイムアタックをするものです。右の模式図のような立体交差を利用した特設コースを2台が同時に走ります。赤で示したスタート地点から2台が青と紺の別々のルートを出発します。1周すると、相手のスタート地点になり、さらにもう1周を走って、結果として自分のスタート地点に戻ってくるタイプのものですので、直接競り合うことはありません。